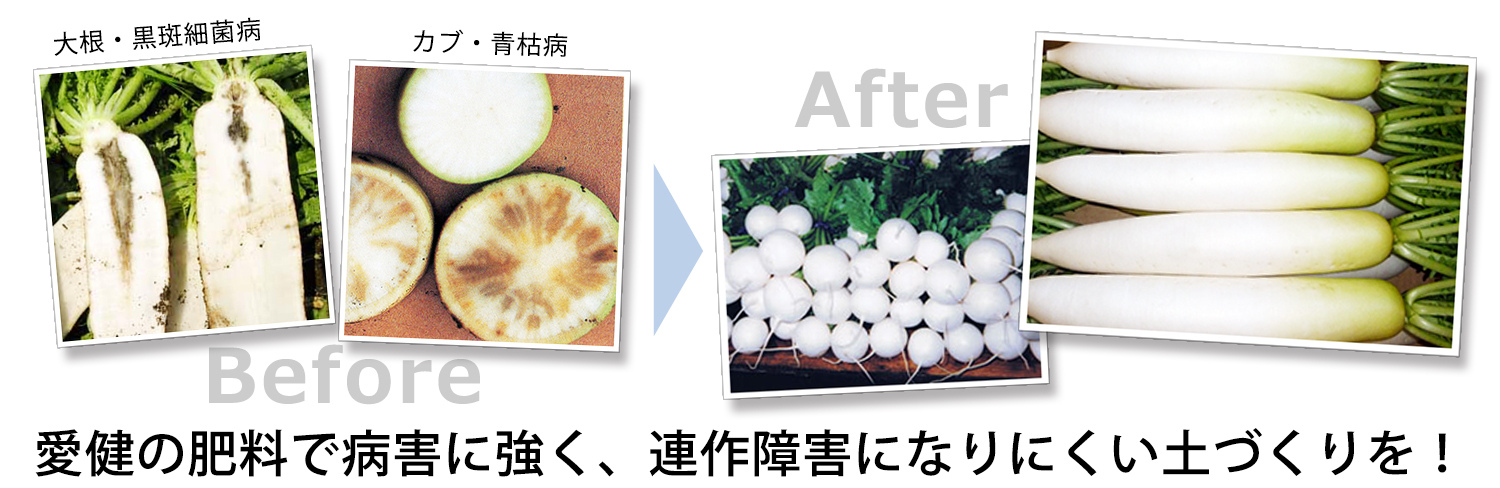
アブラナ科『キャベツ』
アブラナ科。害虫の被害が比較的多い野菜。
葉の数が少ないと結球しないので、
害虫に食害されても、できるかぎり防除して
葉は残すようにする。

黒腐病(くろぐされびょう) 詳しくはコチラ
【黒腐病の症状】
細菌により発生する病気。
病原細菌は、葉のふちの水孔や気孔、虫の食害などによる
傷口などから植物の中へ侵入する。
葉のふちから黄変し、次第に拡大して、葉脈が褐色に変化する。
重症化すると、茎の地際も感染し、茎や根の中が褐変する。
【黒腐病の発生しやすい時期】 3月〜10月


軟腐病(なんぷびょう) 詳しくはコチラ
【軟腐病の症状】
細菌により発生する病気・
病原菌は土壌中に生息し、植物の傷口から侵入する。
ちぎわの茎や葉の幹部などが、淡黄色で水が浸みたような(水浸状)に
変色して、軟化し、腐敗する。
重症化すると株全体が腐敗し、悪臭を放つ。
【軟腐病の発生しやすい時期】 6〜10月


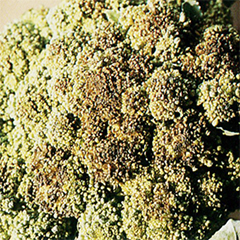

菌核病(きんかくびょう)
【菌核病(の症状】
カビの仲間(糸状菌)により発生する病気。
水か浸みたような(水浸状)の病斑が生じ、次第に拡大する。
病斑は褐色から黒色に変色し、やがて白い綿状のカビに覆われる。
直径数ミリ前後の黒粒(菌核:菌糸が集まってできたカビの集まり)
が形成される。
【菌核病(の発生しやすい時期】 3月〜11月


べと病(べとびょう)
【べと病の症状】
カビの仲間(糸状菌)により発生する病気。
葉に淡褐色の不明瞭は病斑が生じ、葉脈で区切られてくる。
葉裏にはハイ紫色のカビが密生する。
重症化すると病斑は葉の全体に広がり、枯れる。
梅雨や秋などの長雨の時期に発生しやすい。
【べと病の発生しやすい時期】 5月〜10月


モンシロチョウ
【モンシロチョウの特徴】
細かい毛がびっしりと生えた緑色のイモムシ。(別名:アオムシ)
多くの幼虫により、たくさんの葉が食害されてから気づくことが多い。
葉の裏、表にもいる。成長すると食べる量も増える。
【モンシロチョウの防除】
成虫を見かけたら、卵や幼虫の発生に十分注意し、観察する。
発生を確認したら、早めに対処できるように準備する。
葉にいることが多いので、気づいたら取り除く。
できるだけ成長する前に駆除する。
【モンシロチョウの発生しやすい時期】 4〜11月


ウワバ類
【ウワバ類の特徴】
幼虫は緑色のイモムシ型で、腹部の脚(腹脚)を
対に持つのが特徴。頭の方が小さく、身体の後部が太い。
基本的に、葉の裏にいることが多い。キャベツやレタスなど
結球野菜においては、内部より外葉に多く見られる。
【ウワバ類の防除】
飛来してくるので予防は困難。ただし、葉裏にいることと
内部より外葉にいることが多いので被害はそれほど深刻にならない。
数が多くなければ、見つけ次第捕殺する。
個体数が多いようであれば、薬剤で防除する。
【ウワバ類の発生しやすい時期】 4〜11月


ヨトウガ(ヨトウムシ)
【ヨトウガ(ヨトウムシ)の特徴】
ヨトウガ:夜盗蛾(ヨトウムシ:夜盗虫)の名の通り、
夜になって葉を食べる種類もいるが、昼間活動する種類もいる。
広範囲の植物を食べるので、他の作物への被害も拡大する。
【ヨトウガ(ヨトウムシ)の防除】
成虫は飛来するので予防は困難。
塊で産卵されるので、集まっているうちに取り除くのが確実。
卵塊や幼虫は見つけ次第、速やかに捕殺する。
茶色や緑色の粒状の分が残っていたり、穴が開いて被害を受けた痕が
あるのに虫がいないときは、株元の土の中を探す。
まわりの雑草はこまめに除草する。
重症の場合、薬剤散布。
【ヨトウガ(ヨトウムシ)の発生しやすい時期】 4〜10月


有限会社 愛健 -AIKEN-
〒354-0043 埼玉県入間郡三芳町竹間沢 409-5
工場 〒350-1155 埼玉県川越市下赤坂1805-27
TEL : 049-293-9667 FAX : 049-293-9667
Copyright AIKEN All Rights Reserved.